-
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
家でなんとか弾けたかと思った「ダークアイ」も、レッスンで弾くと無残なものだった。
この落差は何が原因なのだろうかと考えてみた。
------------傾向と対策(個人的メモ)-----------------
【1】普段、指の先で押す練習できていない
いつも先生に注意をうけるのだが、私は悪い癖がついてしまっていて、指先でなく、指のはらで弾いてしまう。
特に左手と右手の小指は、第一関節をまげる形ではなく、逆にそらせてしまいがち。
かなりの注意を払わないと、この悪癖はすぐ復活してしまう。
家での練習で指への注意が足りないため、レッスンで正しい形で弾こうとするとボタンの間隔がつかめなくなり戸惑うことになる。
→練習の際も、指のはらで弾いていないか気をつける。
【2】CIAOとBUGARI
楽器の個体差。夜練習はいつもCIAOで行っているが、レッスンでみていただくのはBUGARIなので、ボタンや鍵盤の感触が微妙に違う。
→土日のBUGARI練習をもっと丁寧に行う。
→指の「なんとなく」の感覚で弾くのではなく、このボタンの右ななめ上、その二つ上…とボタンの位置関係をイメージしながら弾く!)
【3】練習不足
特に左手の練習が足りない。
→右より左を多く練習!
【4】基本的な指練習不足
練習の際には練習曲からはじめず、まず基礎練をする。
------------(個人的メモ終わり)-----------------
今回のレッスンで先生に教わったのは、左手の半音階。
あるボタンから、すぐななめ下に下がると半音上の音。
あるボタンから、すぐななめ上に上がると半音下の音。
アコーディオンって、なんて機能的な配列なんだろう!
たとえばCスタートならば、
Cに小指(または薬指)をおき、薬指と人差し指をまるでしゃくとり虫のように動かして、C〜C#〜D〜D#〜E〜と上がっていく。ボタンがなくなったら今度は、同じ要領で下がっていき、Cで終わる。
【発展形】
・Cに慣れたら、FやGなど、いろいろな音階で同じことをする。
・指使いを変えて同じことをする。
・リズムを変えて同じことをする。
この発展形をひとつひとつ行っていったら、ものすごいパターン数になる。
この左手半音階練習を1日1パターンずつ、着実に練習していくというのが、次回レッスンまでの宿題。毎日練習できれば14パターン。でも昨日は練習しないで寝てしまったので…何パターンになることやら。
ボタンはたくさんあって、果てしない感じがしていたけれど、こうやってひとつひとつ規則性を知っていくと、パズルを解いているみたいな感覚で楽しい。
アコーディオン道は奥深い。PR -
もっと時間がほしいと常に思っている。
仕事帰り、「会社さえなければ!一日中好きなだけ練習できるのに…」とよく思う。
学生を見ては「学生はいいなあ、夏休み、冬休み、春休み…それだけ休暇があればどれだけ練習できるだろう…」
では、会社さえなければ、会社を辞めてしまえば、私は一日中アコーディオンを練習するのか?
たぶん弾かないと思う。いや、弾けないというのが正しい。
最近気づいたのだが、何時から何時までという制約なしに好きなだけ練習できる休日にアコーディオンを思う存分練習して「満足した。今日はこのへんでやめておこう」と時計をみると、だいたい2時間半経過している。
今までに弾いた曲をいろいろ弾いてから課題の曲にうつっても、課題の曲だけにしぼって引き続けても、いずれにしても「満足した」と感じるのは不思議なくらい正確に2時間半なのだ。
たぶん、どんなに頑張っても、集中力持続の限界なのだと思う。
食事とトイレと睡眠以外はアコーディオン漬けという生活もあこがれるけれど、結局、そういう環境があっても2時間半以上は弾けないような気がする。(思えば、アコ合宿に行っても、途中で集中力が切れていた…)
だから、「辞めたら…」とかそんな現実逃避はせずに、まずは毎日さわることを目標にしてのんびり自分のペースでやっていくしかないのだ!と現実逃避好きな自分に言い聞かせる。
さて、今週は、帰宅が非常に遅かった火曜以外、とりあえず毎夜1時間くらいはアコーディオンにさわった。
その成果としては、片手ずつ練習していた「ダークアイズ」をようやくなんとか両手で通せるようになった。
しかし、通せるようになったといっても、この曲の理想的な演奏時間の3倍くらいの時間がかかっていて、とてもたどたどしい…。
この曲に取り組み始めたのはいつだったろうかと、このブログをさかのぼってみると、この楽譜をもらったのは12月!
いくらなんでもスローペースすぎるかもしれない。 -
パリに行ったらアコーディオンのお店や楽譜屋さんに行ってみようと思っていた。カブトガニさんにはいくつものお店のアドレスを教えていただいた。
しかし、3日間のうち、1日め(土曜)はパックの市内観光ツアーで半日とられてしまい、2日め(日曜)はまるまる一日ベルサイユ宮殿とその庭園に費やしてしまい、3日めは平日なのになぜか閉まっている店が多く、他の場所などもまわっているうちに、あっという間に時間オーバーに。結局、パリでアコーディオン(楽譜)専門店にいくという計画は失敗に終わってしまった。無念。
意気揚々と出かけた楽譜屋さんOscar Music。
閉まっている店の前で、無念そうににらむ私。
悔しい。本当に悔しい。
やっぱり3日間じゃ短すぎる!
Pigalleのまわりはギター中心の楽器屋さんが多かった。
ちょっぴりお茶の水の楽器屋街のような雰囲気。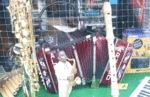
一日め、バスツアーの帰りに迷い込んだRome通りにも楽器屋さん通りのようなものがあった。
こちらはPigalleよりもアカデミックな雰囲気が強く、バイオリン工房や管楽器、弦楽器を専門に扱うお店やピアノ譜専門店などが目立った。バイオリンらしきケースを背負った人と何人もすれちがったので、もしかしたらこの近くに音楽学校があるのかもしれない。
写真は、たまたまショウウインドウで見つけたバンドネオン。
***********************************
パリに行かれる方のために、先日コメント欄で教えていただいたパリのアコーディオン店情報をこちらに転載いたします。 -
仕事帰りに一本の電話。
以前通っていたアコーディオン教室のFさんからだった。
「今度、3月26日に発表会があるんだけどね」
も、もしやこの電話は…と思った予感は的中した。
…というわけで、去年にひきつづき、アコーディオン教室発表会の司会を引き受けてしまった。
冷静になって考えれば、気のきいたコメント一つ言えない私よりも司会の上手そうな人はたくさんいることだし、やめておくのが正解だったのではないかとも思う。
去年も引き受けてからが大変だった。「上手な司会の仕方」のようなハウツー本を焦って読んだり…、演奏で参加したときよりも前夜は緊張したし。
が、一度は中断していたアコーディオンレッスンに再トライしようと決意させてくれたのは、他ならぬ前回の発表会だ。
去年、発表会の司会をしていなければ、いまレッスンに通っていなかっただろうし、MIDIアコも買っていなかっただろうし、かるふーるのことも知らなかっただろうし、こうしてアコーディオンブログまで書いてどっぷりアコーディオンにハマった毎日もなかっただろう。
アコーディオン再開の契機に感謝の念を込めて、今年も司会にチャレンジしよう。
去年は本番当日、みんなの演奏曲のコメントを先生に考えてもらったりと、かなりダメダメで甘えまくった司会っぷりだったので、今回はもう少しリラックスして自分の言葉でコメントができるようにしたい。 -
本当のレッスン日は土曜日なのだが、2/3は出発日なので、レッスンを月曜夜に振り替えてもらった。
平日の夜、仕事が終わってから、レッスンに向かうのは初めて。
レッスンは40分なのだが、今日は私が最後だったので、それよりもかなり長くレッスンしてもらった。(ラッキー♪)
というか、気づくともう夜の9時だったのだ。先生のレッスンは楽しくていつもあっという間に時間が過ぎてしまう。
今日はカデンツなどについても教わった。
子供の頃、音楽教室に通っていて「スケールとカデンツ」というレッスンがあったことを思い出した。ただそのときは、ひたすら丸暗記して練習した記憶だけがある。なにか理屈を少しは教わったような気もするのだが、音楽理論、音楽用語のようなものは、いまとなってはほとんど身についていない。たぶん子供のときの私はそういうことに興味がなかったのだ。だから頭にはいらなかった。
でもいまは音楽理論のようなものにも少し興味があるので、いろいろ教えていただくと、「なるほど!」という発見があって楽しい。
ところで、「アコーディオン」の意味は、和音の器というらしい。
そういえば、私はアコーディオンを習い始めたとき、アコーディオンはコードボタンを押すだけでコードが弾けるから、(コードを理解していない)私にはうってつけだなあと思ったものだ。
(でも、ドイツの音大のアコーディオン科は、フリーベース奏者以外入学できないらしい。フリーベース以外のアコーディオンは簡単すぎるからという理由だそうな。)
今日は長かった分、教わった内容もかなりたっぷり。
うまくまとまらないけれど、いろいろわかってくると少し楽しい。 -
先生は「ここはこういうふうに弾きなさい」「これは○○という意味ですよ」というような講義的なレッスンをしない。どういうふうに弾きたいか、この符号はどういう意味か、まず生徒に質問を投げかける。
なんとなく知っているような符号でも、あらためて「これは日本語でいうとどういう意味?」と訊かれると、私は答えられないことが多い。つまり、きちんとわかっていないのだ。
今日のレッスンでは、教本の練習曲を一回聴いてもらったあと、「この曲を大きく分割してみると、その中のどの部分を盛り上げたい?」「このフレーズの中ではどの音をきかせたい?」と先生に訊かれて、返事に窮した。
その練習曲には、例えばfとかpとか<とか>とかritとかの指定はまるっきり入っていない。
で、それをいいことに、私はなんにも考えずにただただ音を出して弾いていたので。
ここは静かになって、この部分で盛り上がって、少しゆっくりになって…と楽譜に書き込みを入れていって、もう一度弾いてみたら違う曲のようになった。
どうも楽譜があるとその表記通りに弾ければそれでいいかなという気になってしまうけれど、どんな曲でも「どういうふうに弾こうかな」と自分なりに考えることが必要なのだ。
メロディの聞かせどころ(?)がわからないときは、声に出して歌ってみるといいらしい。
外国語の習得と同じで、間違いを恐れずどんどんやってみて〜と先生に言われてしまった。
確かに、英会話なんかでも間違いを恐れて尻込みしがちなタイプでした私…。
さて、それはそうと、次回レッスンから独奏だけでなく三重奏の練習もすることになった。
譜面をいただいたけれど曲を聴いた事がないのでちょっと心配。
他の二人の足を引っ張ってしまわないようしっかり練習しなくては! -
朝起きたら窓の外は一面真っ白・・・。
いつもは雪が降るとなんだか嬉しいのだが、今日はレッスンの日なのでがあまり歓迎できない。
大好きなアコーディオンも雨の日や嵐の日や台風の日や雪の日は、その重さがちょっとうらめしくなる。
繊細なアコーディオンは、濡れるのは大敵。
雨や雪の日には、登山用品屋で購入したカバーが欠かせない。
すっぽりとこのカバーをかければちょっとくらいの水滴ならしのげる。 -
2月のかるふーるでは、Akkordeon.jpの川井さんがSEMのCIAOとCIAOが埋め込まれたボタンアコーディオンSEM Super Prince Specialと、木目調で素敵なアルプススタイルのアコLanzingerを持って参加されたので、店内はアコーディオン屋さんのように楽器とケースでひしめいた。
CUAO(ピアノキー)の特徴は以下の通り。
・41鍵
・120ベース
・内臓音源は399種類
・音源プリセット24
・重さ7kg
川井さんのすごいところは、高価なアコーディオンを「自由に」さわらせてくれる所だ。
よく楽器屋さんでは、高価な楽器はガラスケースの中にしまわれていて、触らせて欲しいとなかなか頼みにくかったりする。勇気を出して店員さんに声をかけても、そこからまた気まずかったりする。
試し弾きの間、「楽器購入の声はまだかまだか」(実際はそうではないのだろうけど、お客としてはそう感じるのです)といわんばかりに店員さんが傍らで待ち構えている場合も多く、「買うわけじゃないけれどさわってみたい」「へただけどちょっと弾いてみたい」私は、とても気になってしまう。
その点、川井さんは「どんどん弾いて、音を確かめてみて」と気さくに声をかけてくれて、高価な楽器を惜しげもなく試奏させてくれる。
「買うわけじゃないけれどさわってみたい」「へただけどちょっと弾いてみたい」私には願ったりかなったりのもったいない楽器屋さん。
(そうはいっても、気に入ったアコがあったら買わないと…ね^^;)
かるふーる交流会が終わった後も、川井さんのアコーディオンは大人気だった。
たぶんその場にいたほとんどの方がCIAOを一回は弾いたのではないだろうか。
CIAOは399種類の音が出る。
サックスとかグランドピアノとかバイオリンとかハープとか…ホントに色んな音が出る。
民族楽器の音色なら民族音楽、ジャズピアノならジャズの名曲、ボイスならオペラなど、音から連想した「ふさわしい曲」が即座に奏でられるととても楽しいと思う。
Sarasaの岩城さんがCIAOを試奏するのを見ていたら、岩城さんは出た音を聴いて、即興で遊んでいた。
楽しそうな岩城さんの姿を見て、私のCIAO君はもっぱら「ヘッドホン練習専用アコーディオン」と化してしまっているけれど、もっと399の音を遊んであげないと可哀相かなと思った。 -
アコーディオン喫茶かるふーるには、アコーディオン以外の楽器も集まってくる。
アコーディオン喫茶だからといってアコーディオンに限定されないところがとても好きだ。
2月のかるふーるにも、珍しい楽器が集まって来た。
マトリョーミン、コンサーティナ、ザフーン。
この3つの楽器のいずれも私は前々から興味を抱いていた。
※写真はネットで拾ってきたものです。
マトリョーミンはmixiでロシア(私はロシア民謡好き)関係のコミュニティをまわっていて 半年くらい前に知っていたのだが、実際に楽器を、そして演奏を見たのは今回が初めて。
こんなふうに奏でるのかあ!マトリョーミンって!
とても愛らしいマトリョーシカに手をかざし、まるで超能力者かマリックのような「ハンドパワー」で不思議な音を引き出している姿はかなりユニークだ。
ほなほなさんのマトリョーミン演奏を聞いてSarasaのお二人が「これは絶対音感がないと弾けない楽器だね〜」と話していた。
確かにそうだと思う。キーを押せばドやレやミが出る鍵盤では味わえない醍醐味があるのだろう。奏者の手のしめりけなどでも音が変わってくるとのこと。なんと繊細かつ感覚的な楽器なんだろう!
※写真はネットで拾ってきたものです。
そして、この日はコンサーティナが2種類も!
ひとつはくどうえりさんのダイアトニック、もうひとつはほなほなさんのクロマチック。
見てみると、どちらも可愛い。ダイアトニックのほうがボタンが大きくて弾きやすそうかなという第一印象。
かねてから私が欲しいなと思っていたのは、ほなほなさんのコンサーティナとちょうど
同じタイプのものだった。ホーナーの押し引き同音の48ボタン・イングリッシュコンサーティナ。
ちょっと触らせてもらった感じでは、(アコーディオンにくらべて)小さいのになかなかきれいな音が出る。ボタン配列を覚えないと、チューリップ程度しか弾けなそうだけれど、練習のしがいのありそうな楽しそうな楽器!やっぱり面白そう!欲しい!
パリ旅行で散財したのちは、まじめにお金をためて(!)買いたいと思う。
※写真はネットで拾ってきたものです。
竹之内君が持って来たザフーン。
これを私は数年前に新宿で買おうかどうか迷った記憶がある。
路上で日本語の上手な外人さんがデモンストレーションをしながら販売していたのだ。
ボディは竹でできていてみかけは縦笛のようだが、リードで鳴らすのでサックスのような気持ちのよいやわらかい音が出る楽器。
とても私の好きな音だったのだが購入は断念した。なぜ買わなかったかというと、試奏してみて全然音が出せなかったから。中学のとき吹奏楽部に仮入部してトランペットをさわらせてもらったがわたしひとり全く音が出せず赤面したトラウマを思い出したくらい、全然鳴らせなかったのだ。
そんな私の苦い経験にくらべ、竹之内君は気持ちの良い澄んだ音を出していた!彼はかるふーるで会うたびに違う楽器を演奏しているけれど、なんでも簡単に弾いてしまう感じで、すごいと思う。
ザフーンといえば、数カ月前に和圭先生も「今日買ったばかり!」と言ってちょっと吹いてくれたっけ。
そしてそこでさわらせてもらった時も私はまったく音が出せなかったっけ。 -
今回のゲストはSarasa。
ライブ開始直前にかるふーるにすべりこんだので、あいていたのは一番前の席だった。
少し手をのばせばアコーディオンにふれてしまいそうなくらいSarasaの福島さんに近い。大迫力!
指使いも蛇腹使いもバッチリ拝見することができる!
しかし、真正面なので、トークをするときなどは思いっきり目があってなかなか恥ずかしい…。
岩城さんはニコニコしていてとても楽しそうだがMCが苦手とのことで、MCの大半は福島さんが軽妙なちょっぴりcoba風トークを繰り広げる。
「僕たちの演奏は、カニカマのようなものです!」
なんでそんなに自虐的!?
私はSarasaの演奏を聴くのは初めてだったのだが、噂どおりの素敵なデュオだった。
プロのミュージシャンの舞台を見ると必ず感じるのが「楽しんで」演奏しているということなのだが、Sarasaのお二人には特にそれを強く感じた。
お二人は「夫婦デュオ?」(二人は夫婦デュオではないのです!既婚者同士のデュオというのが驚きです)と思ってしまうくらいのやさしいアイコンタクトをしてガリアーノをピアソラをcobaを「楽しんで」いる。
例えばアコーディオンと別の楽器のデュオだと、一方がメインで一方がバッキングで…とパート割りのようなものが決まりがちだが、アコーディオンデュオSarasaの場合は、メロディ、バッキングともに交互にナチュラルに入れ替わっていてお互いの見せ場がうまくからみあっている感じが心地良い。
MCではニコニコほのぼのとした雰囲気だけれど、演奏はドラマチックな曲が多くてそのギャップもとてもいい感じ。至近距離だったのでアディオス・ノニーノは大迫力でドキドキした。ジャジーな(?)パリ空もすごくカッコよかった。
福島さんはcobaさんが本当にお好きのようで、cobaさんの曲はひときわ生き生きとしていた。
やはり好きなミュージシャンへのオマージュはまぶしい。
岩城さんはニコニコ笑っていてとてもやさしい音色を紡いだかと思うと、華奢な身体に見合わないようなダイナミックな音を奏でる。彼女の「マルゴーのワルツ」はやはり凄かった。ベローズラバーズで檜山さんが「壊れんばかりに弾きたい」と言っていたけれど、まさに彼女の演奏は「壊れんばかり」のわきあがるドラマを感じた。
彼女の「マルゴーのワルツ」は、実は2002年のJAA国際アコーディオンコンクールで拝見したことがあるのだが、あの時よりもさらに深みが増して情熱的だった。コンクールのホールの座席からでは遠かったけれど、今回はこんなに近い距離で聴くことができてとても心がしびれた。
岩城さんの「毎日、アコーディオンで2時間遊ぶ」「目的を決めずに」という言葉がとても印象的だった。
「毎日2時間」という部分も、「アコーディオンで遊ぶ」という部分も、私は見習わないと…。
さてさて、次回、3月のゲスト演奏は、オランさん!
(えりさん、ありがとうございます!)
私は常日頃、「オランさんが好き」「オランさんを聴いてアコーディオンを始めた」などと言っている割に、最近の彼女のライブに全然いけていない。もう今から3月が楽しみで仕方ない。


