"Accordion"カテゴリーの記事一覧
-
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
わたしが「もっと弾かなくちゃ!」とやる気モード全開になるのは、たいていレッスン直後、ライブに行った直後。

レッスンの帰り、途中下車して、多摩川河川敷に向かった。
ここは、通勤途中に電車の中からみていていつも気になっていた。
「あそこなら、周りを全然気にしないで思う存分、のびのびと弾けそう!」
案の定、存分に音の出せる、すてきな練習場所だった。
利用者の多いにぎやかな公園は、人目が気になるから練習しにくい。
また、利用者の少ないしずかな公園でも、住宅が近いと、近隣の方への迷惑になってしまうので練習しにくい。
その点、河川敷は最適な場所だ。
なにしろ多摩川は長いし、広い。談笑しながらウオーキングする人たち、犬の散歩をする人、ジョギングをする人、お弁当をもってきてお昼を楽しむ人、絵を描く人、サッカーをする少年達(グラウンドがあるので)・・・いろいろな人達がいる。そして住宅からは距離がある。
川べりに腰掛け、水鳥たちを眺めながら弾いた。
部屋で弾いているときにくらべ、すぐ空気が足りなくなる。
いつも4小節くらいで蛇腹をかえしていたけれど、2小節くらいで蛇腹をかえす。知らず知らずに大きな音がでている。
実は、部屋で弾いているときは、「他の人のアコにくらべて私のアコはあまり良い音がしない」なんて不満を抱いていた。
でも、屋外で気持ち良く弾いたら、なんていい音なんだろうと思った。
特にベースの低音の響きが好きだ。なんていい音なんだろうと思って、いとおしくなった。
いつも部屋で小さな音で弾いて、お前の良さをいかしてあげられなくてごめんねと思った。
しあわせいっぱいの外練習だったけれど、途中からビュンビュンつめたい風がふくようになって芯からひえてしまったので一時間半ほどで早々引き上げた。まだちょっと外練習には早いかな。PR -
eteさんやmileさんのブログでみて、ちょっと気になっていたミニミニアコーディオン(押し引き異音)を購入。
色は、赤、青、黒、白があって、eteさんが青、mileさんが白を持っているので、私は違う色にしようと思ったのだが、白の可愛い感じに負けて、白を選んだ。
手に持ってみると、ちっちゃ〜い、かわい〜い、意外と音は出る〜、とても満足。
しかし、なかなか演奏にはならない。
押し引き異音は一筋縄ではいかない。
右手が7ボタン(14音)
左手が3ボタン(2コードと2ベースと空気抜きボタン)
↑こう書くと、なんとか簡単な曲なら弾けそうな気がするのだけれど、
やはり押し引き異音は一筋縄ではいかない。
何か一曲くらい弾けるようになりたい。 -
ゲストコンサートの後は、演奏交流会。
前に立って一人ずつ自己紹介トークや演奏をする。
前に立ってみると思うことなのだが、かるふーる交流会で受ける視線はあたたかいのだが、ドバーンと太いということ。聴く側の目ヂカラをとても感じる。 -
3月のかるふーるに行って来た。
ゲストコンサートは私がかねてより熱望していたオランさん。3月のゲストを知った1月からこの日をものすごく楽しみにしていた。
にもかかわらず、(時間ギリギリで行動してしまう私の性癖が何よりも諸悪の根源なのだが)日曜昼間のY線とC線の乗り継ぎの悪さを恨みつつ、開演13:30を15分ほど遅刻してお店についた。
ドアをあけると、私の好きな「たったひとつの月」の弾き語り中だった。(あーあ。)
オランさんは途中で、「私はよく癒し系といわれたり、パンクといわれたり」とMCがあったが、ほんとうにみるたびに印象が違う。場所やお客によって変えている面もあるのだろうか?
なんて色々な引き出しを持っている人なんだろうとあらためて感じた。
もともとオランさんは一言ではいえない独特のアコーディオン弾きだとは感じていた。
たとえば、私はオランさんの大ファンなのだが、彼女をきいたことのない人に、「オランさんはどんな音楽をやるの?」と聞かれても言葉ではうまく答えられない。「とにかくまずは実際に聞いてみて」と答えるだろう。
実際に聴いてみないとわからない独特の雰囲気。そしてその時の心理状況によっても受けるイメージはかなり違う。
オランさんを初めて見たのは、渋谷アピアだった。
精神的に余裕のなかった私はその頃、アピアの暗いアングラな雰囲気がとても好きで、よく行っていた。その頃のオランさんの歌は今よりも毒が強くて、アピアによく似合っていた気がするし、その頃の私もブラックな雰囲気を好んでいた。
その後、アピアは改装して小奇麗になってしまい、私はあまり寄り付かなくなった。
寄り付かなくなった間に、私はなんとなく落ち着いた。
そして、なんとなく落ち着いた今の私は、かるふーるのようなやわらかい雰囲気を好むようになった。
そんな変化もあってか、今回はオランさんの曲の中でも「さんぽ」や「たね」「とりのうんちにくるまれて」など、やさしい曲がとても心にしみた。
そんな自分を数年前にくらべずいぶん変わったものだと思った。(ちなみに以前は、「みんな頭に赤い傷」や「まんげきょう」が一番好きだった。)
オランさんのパナシェの一員としての姿もまた全然違ったけれど、かるふーるでのライブは格段に違う印象をみた。
スポットライトではなく自然光のもと、明るさとやさしさの空気の中での等身大の演奏は、大事なのは曲や弾き方や楽器ではなく、おんがくへの向き合い方と教えてくれる気がする。
オランさんにとっては音楽は特別なことではなく、生活感情に密着している。言葉を発するときに、自然と息を吸って自然と息を吐くようなこと。
曲や弾き方や楽器ではなく、おんがくへの向き合い方、が透けてみえるような演奏だった。
日常と音楽は別のものではなく、日常は音楽にすることができる。
とても有意義な日曜の午後だった。 -
ネットをさまよっていたら、こんなものを見つけました。
(※このアプリを使うためにはShockwaveプラグイン(無償ダウンロード)が必要です。)
http://www.tama.or.jp/%7Etane/new/accobass.html -
akkordeon.jpの川井さんからご紹介していただいたCIAO仲間、Aさんにお会いした。
私がSEM社のMIDIアコーディオンCIAOを買ったのは、2005年7月のことだが、CIAO仲間に会うのはこれが初めて。
壁の薄いアパートに住み、仕事からの帰宅の遅い私の購入理由は、ヘッドホンをつけて近隣に音を漏らさずに練習したい!という願望が主だったため、CIAOにはおよそ400種類もの様々な音色がインプットされているというのにも関わらず、その機能は使いこなせているとはいえない。
2月19日(日)八王子の公民館にて、演歌サークルの伴奏をAさんがCIAOで行うとのことで、私は一路、八王子に向かった。
演歌は決して詳しくない私である。
訪問目的は、実際にバンドでその機能を駆使されているAさんの演奏を聞き勉強させてもらうこと。
お会いしてみると、Aさんは私のようなアコ初心者が「CIAO仲間」などというのもおこがましいような、アコ歴うん十年の大ベテランプレイヤーであった。
物腰やわらかく、とても紳士な方で、若輩者の私の愚問にも丁寧に答えてくださった。
Aさんは電気系にもお詳しいらしく、ローランドの120Wアンプの裏に木材や金具をうまく使ってSEMのプリアンプを貼り付け、コードを綺麗に巻きつけ、見事な「アンプ一体型SEMシステム」を自作なさっていた。これはイイ! 持ち運びもスマートだし、何より演奏前の準備がシンプル(アンプを電源につないで、CIAO本体にコードをつなぐだけ!)だ。じっくりと取り付けの仕組みを見させていただいた。(今度、電気系作業が得意な知人に作ってもらおう)
伴奏はアコーディオンだけでなく、ドラム、ギター、ベース、サックス、キーボードの、六人編成バンドだった。
私ははじめ、Aさんも演歌がお好きで、演歌を歌う会の一員なのかと誤解していたのだが、実際はそうではなく、演歌を歌う会から「演歌の生バンド伴奏をしてほしい」とオファーがきて、出張演奏しているバンドらしい。
演奏後、バンドのメンバーの方からお話をうかがうと、楽器歴うん十年の方ばかりで、ロックがお好きだったり、ジャズがお好きだったり、音楽の好みもいろいろ。
皆さん口をそろえておっしゃるのは、
「演歌をなめちゃだめだ。演歌は勉強になる」
「歌の会」で歌われるのは、新曲ばかりなので、レパートリーはどんどん増えていく。しかも個人個人のリクエストによる選曲なので、一回レパートリーとして採譜し練習したものでも、それ以降リクエストする会員がいなければ、お蔵入りになる可能性が高い。
確かに私が知っている曲はなかった。なつメロではなく、流行歌だから、どんどん演奏曲は入れ替わっていく。
演歌のカラオケの音の重なりを、6パートでうまく振り分けた編曲、Aさんが主に行っているという。オカズや間奏など、アコーディオンとサックスがうまくからみあっていて、音がふくらむ。
Aさんは、基本的にはMMの音色でオカズを入れ、前奏部分や間奏部分などでパッと音色を切り替えて曲を華やかにしていた。演歌カラオケにすごくむいている気がした。
「初見の練習になるよ」
「“うた”のオカズのアドリブをとっさに入れるなど、最終的には独奏にも役立つよ」
バンドに誘っていただいたけれど、私はまだまだドヘタなのでとてもじゃないけれど無理だ…。
聞けば、大ベテランの方ばかりのバンドなので、練習は、月1回の「歌う会」伴奏の数時間前に一度あわせるだけらしい。
ジャズやロックやクラシックや、極めたいジャンルを他に持っていた上で、さらなる鍛錬の場として「演歌伴奏」をしているのだ。皆さんのお話をうかがって、スタンスが趣味の領域ではなくセミプロだと思った。
「歌う会」の歌い手さん達を含め、会場にいる方はどの人もとても生き生きしていたのが印象的だった。 -
家でなんとか弾けたかと思った「ダークアイ」も、レッスンで弾くと無残なものだった。
この落差は何が原因なのだろうかと考えてみた。
------------傾向と対策(個人的メモ)-----------------
【1】普段、指の先で押す練習できていない
いつも先生に注意をうけるのだが、私は悪い癖がついてしまっていて、指先でなく、指のはらで弾いてしまう。
特に左手と右手の小指は、第一関節をまげる形ではなく、逆にそらせてしまいがち。
かなりの注意を払わないと、この悪癖はすぐ復活してしまう。
家での練習で指への注意が足りないため、レッスンで正しい形で弾こうとするとボタンの間隔がつかめなくなり戸惑うことになる。
→練習の際も、指のはらで弾いていないか気をつける。
【2】CIAOとBUGARI
楽器の個体差。夜練習はいつもCIAOで行っているが、レッスンでみていただくのはBUGARIなので、ボタンや鍵盤の感触が微妙に違う。
→土日のBUGARI練習をもっと丁寧に行う。
→指の「なんとなく」の感覚で弾くのではなく、このボタンの右ななめ上、その二つ上…とボタンの位置関係をイメージしながら弾く!)
【3】練習不足
特に左手の練習が足りない。
→右より左を多く練習!
【4】基本的な指練習不足
練習の際には練習曲からはじめず、まず基礎練をする。
------------(個人的メモ終わり)-----------------
今回のレッスンで先生に教わったのは、左手の半音階。
あるボタンから、すぐななめ下に下がると半音上の音。
あるボタンから、すぐななめ上に上がると半音下の音。
アコーディオンって、なんて機能的な配列なんだろう!
たとえばCスタートならば、
Cに小指(または薬指)をおき、薬指と人差し指をまるでしゃくとり虫のように動かして、C〜C#〜D〜D#〜E〜と上がっていく。ボタンがなくなったら今度は、同じ要領で下がっていき、Cで終わる。
【発展形】
・Cに慣れたら、FやGなど、いろいろな音階で同じことをする。
・指使いを変えて同じことをする。
・リズムを変えて同じことをする。
この発展形をひとつひとつ行っていったら、ものすごいパターン数になる。
この左手半音階練習を1日1パターンずつ、着実に練習していくというのが、次回レッスンまでの宿題。毎日練習できれば14パターン。でも昨日は練習しないで寝てしまったので…何パターンになることやら。
ボタンはたくさんあって、果てしない感じがしていたけれど、こうやってひとつひとつ規則性を知っていくと、パズルを解いているみたいな感覚で楽しい。
アコーディオン道は奥深い。 -
もっと時間がほしいと常に思っている。
仕事帰り、「会社さえなければ!一日中好きなだけ練習できるのに…」とよく思う。
学生を見ては「学生はいいなあ、夏休み、冬休み、春休み…それだけ休暇があればどれだけ練習できるだろう…」
では、会社さえなければ、会社を辞めてしまえば、私は一日中アコーディオンを練習するのか?
たぶん弾かないと思う。いや、弾けないというのが正しい。
最近気づいたのだが、何時から何時までという制約なしに好きなだけ練習できる休日にアコーディオンを思う存分練習して「満足した。今日はこのへんでやめておこう」と時計をみると、だいたい2時間半経過している。
今までに弾いた曲をいろいろ弾いてから課題の曲にうつっても、課題の曲だけにしぼって引き続けても、いずれにしても「満足した」と感じるのは不思議なくらい正確に2時間半なのだ。
たぶん、どんなに頑張っても、集中力持続の限界なのだと思う。
食事とトイレと睡眠以外はアコーディオン漬けという生活もあこがれるけれど、結局、そういう環境があっても2時間半以上は弾けないような気がする。(思えば、アコ合宿に行っても、途中で集中力が切れていた…)
だから、「辞めたら…」とかそんな現実逃避はせずに、まずは毎日さわることを目標にしてのんびり自分のペースでやっていくしかないのだ!と現実逃避好きな自分に言い聞かせる。
さて、今週は、帰宅が非常に遅かった火曜以外、とりあえず毎夜1時間くらいはアコーディオンにさわった。
その成果としては、片手ずつ練習していた「ダークアイズ」をようやくなんとか両手で通せるようになった。
しかし、通せるようになったといっても、この曲の理想的な演奏時間の3倍くらいの時間がかかっていて、とてもたどたどしい…。
この曲に取り組み始めたのはいつだったろうかと、このブログをさかのぼってみると、この楽譜をもらったのは12月!
いくらなんでもスローペースすぎるかもしれない。 -
パリに行ったらアコーディオンのお店や楽譜屋さんに行ってみようと思っていた。カブトガニさんにはいくつものお店のアドレスを教えていただいた。
しかし、3日間のうち、1日め(土曜)はパックの市内観光ツアーで半日とられてしまい、2日め(日曜)はまるまる一日ベルサイユ宮殿とその庭園に費やしてしまい、3日めは平日なのになぜか閉まっている店が多く、他の場所などもまわっているうちに、あっという間に時間オーバーに。結局、パリでアコーディオン(楽譜)専門店にいくという計画は失敗に終わってしまった。無念。
意気揚々と出かけた楽譜屋さんOscar Music。
閉まっている店の前で、無念そうににらむ私。
悔しい。本当に悔しい。
やっぱり3日間じゃ短すぎる!
Pigalleのまわりはギター中心の楽器屋さんが多かった。
ちょっぴりお茶の水の楽器屋街のような雰囲気。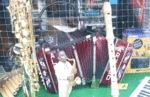
一日め、バスツアーの帰りに迷い込んだRome通りにも楽器屋さん通りのようなものがあった。
こちらはPigalleよりもアカデミックな雰囲気が強く、バイオリン工房や管楽器、弦楽器を専門に扱うお店やピアノ譜専門店などが目立った。バイオリンらしきケースを背負った人と何人もすれちがったので、もしかしたらこの近くに音楽学校があるのかもしれない。
写真は、たまたまショウウインドウで見つけたバンドネオン。
***********************************
パリに行かれる方のために、先日コメント欄で教えていただいたパリのアコーディオン店情報をこちらに転載いたします。 -
仕事帰りに一本の電話。
以前通っていたアコーディオン教室のFさんからだった。
「今度、3月26日に発表会があるんだけどね」
も、もしやこの電話は…と思った予感は的中した。
…というわけで、去年にひきつづき、アコーディオン教室発表会の司会を引き受けてしまった。
冷静になって考えれば、気のきいたコメント一つ言えない私よりも司会の上手そうな人はたくさんいることだし、やめておくのが正解だったのではないかとも思う。
去年も引き受けてからが大変だった。「上手な司会の仕方」のようなハウツー本を焦って読んだり…、演奏で参加したときよりも前夜は緊張したし。
が、一度は中断していたアコーディオンレッスンに再トライしようと決意させてくれたのは、他ならぬ前回の発表会だ。
去年、発表会の司会をしていなければ、いまレッスンに通っていなかっただろうし、MIDIアコも買っていなかっただろうし、かるふーるのことも知らなかっただろうし、こうしてアコーディオンブログまで書いてどっぷりアコーディオンにハマった毎日もなかっただろう。
アコーディオン再開の契機に感謝の念を込めて、今年も司会にチャレンジしよう。
去年は本番当日、みんなの演奏曲のコメントを先生に考えてもらったりと、かなりダメダメで甘えまくった司会っぷりだったので、今回はもう少しリラックスして自分の言葉でコメントができるようにしたい。

